ほっと一息
2025.04.08
国際協同組合年
JA広報通信2025年4月号
●2025国際協同組合年全国実行委員会事務局
日本の協同組合の歴史
協同組合は人々が助け合い、みんなの幸せの実現に向けて、より良い暮らしや社会を目指す自主・自立の経済組織であり、運動体です。
協同組合はその時々の組合員の課題達成に取り組んできた歴史を持ちます。
今回は日本の協同組合の歴史と特徴について解説します。
■ 日本の協同組合の歴史
江戸時代末期、二宮尊徳が経済的に苦しむ藩士のための「五常講」という信用組合のような制度を、大原幽学が「先祖株組合」という土地を出資の代わりにしてその収益で農民などが助け合って生活していく仕組みをつくりました。
大正時代、協同組合運動の父と呼ばれる賀川豊彦は、貧しい人々の救済のため労働運動、農民運動、普通選挙運動など社会改革運動を推進しました。彼が設立した神戸購買組合は現在まで続く協同組合の祖となっています。
協同組合が全国的につくられるようになった契機には、産業組合法(1900年)の成立があります。その後農業協同組合法(47年)をはじめとした個別の協同組合法が順次制定され、2022年10月には労働者協同組合法が施行されています。
■ 協同組合の特徴
世界的に見ると「協同組合基本法」のような横断的な法律が存在している国が多いですが、日本ではさまざまな種類の協同組合が個別法に基づいて事業を行っており、これは日本の協同組合の特徴ともいえます。
日本では、協同組合に延べ1億820万人の組合員が加入し、協同組合が生み出す付加価値の総額は4兆9000億円にもなります(※1)。また、日本における協同組合への加入率は個人ベースで46・5%、世帯ベースで51・4%と推計されています(※2)。
国際協同組合年を迎えた今、協同組合同士が連携を深め、社会課題の解決に一層取り組んでいくことが期待されています。
「2025国際協同組合年(IYC2025)のページ」
日本協同組合連携機構
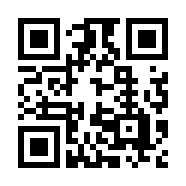
※1『事業年度版 協同組合統計表』(2024年3月:日本協同組合連携機構)。
複数組合に加入の場合は組合員数を重複計上。
※2『協同組合に関する全国意識調査2022』(2023年3月:日本協同組合連携機構)



