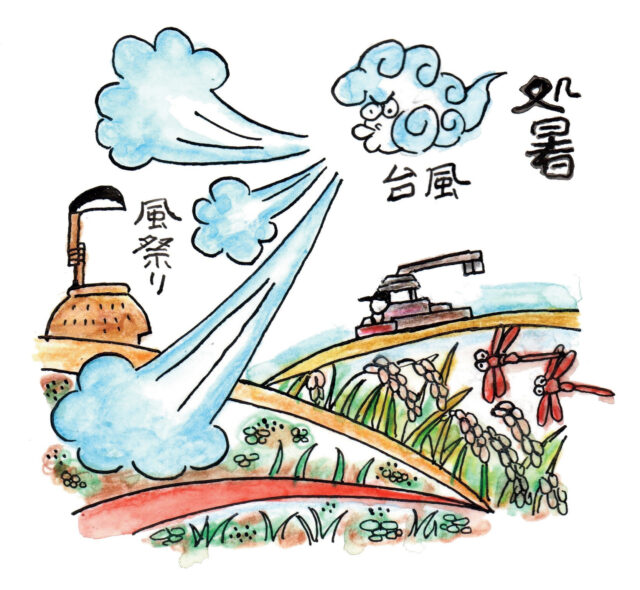ほっと一息
2025.07.16
農と歳時記
JA広報通信2025年7月号
和文化講師●滝井ひかる
立秋・処暑・二百十日
■ 立秋(りっしゅう 2025年は8月7日)
月遅れの七夕祭りが行われる頃、二十四節気では立秋を迎えます。立秋を過ぎたら「暑中見舞い」ではなく「残暑見舞い」へと替わります。
その後に月遅れのお盆が行われます。ご先祖さまを供養する仏教行事です。13日の夕方、ご先祖さまの霊が迷わず帰ってこられるように、麻の茎を乾燥させた麻幹(おがら)で迎え火をたきます。そして15日の夜、または16日の朝に送り火をたいてご先祖さまを送ります。その最たるものが京都の五山送り火です。夏の風物詩である盆踊りも、本来はご先祖さまを供養して送るための踊りです。
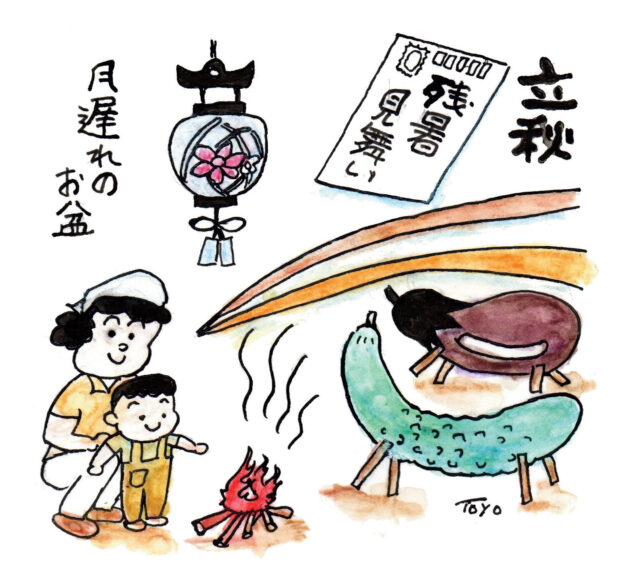
■ 処暑・二百十日(しょしょ・にひゃくとおか 2025年は8月23日・8月31日)
二十四節気の処暑は暑さのピークを越える頃ですが、まだまだ残暑は続きます。それでも時折吹く涼しい風に、少しずつ秋の気配を感じます。
また、立春から210日目を指す二百十日は、日本の農事と深く結び付いている雑節の一つです。風が起こりやすい日とされ、頻繁に台風が発生する頃でもあります。農作物が被害に遭わないように、風を鎮めるため各地で風祭りが行われます。
昔から台風のことを、野を吹き分けるように強く吹くことから「野分(のわき)」と呼びます。『枕草子』や『源氏物語』にも出てくる言葉です。大きな被害をもたらす台風ですが、風情がある名前でも呼ばれているのですね。