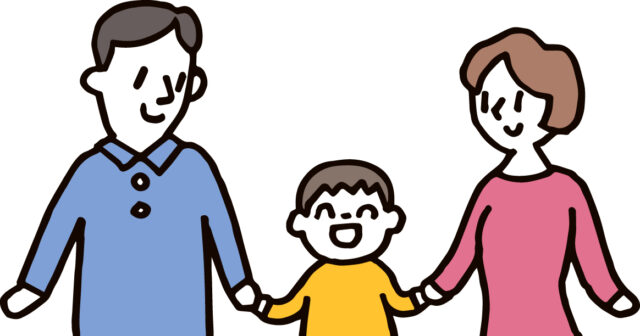お知らせ
2025.03.21
資産管理の法律ガイド
JA広報通信2025年3月号
JA全中・JAまちづくり情報センター 顧問弁護士●草薙一郎
親族法について その19
今回は認知について説明します。
今まで嫡出である子についての説明をしましたが、嫡出でない子に関して、法律上の子としての効果が生じる行為を認知といいます。民法の認知は任意認知と裁判手続きを経て認める強制認知の二つがあります。
民法779条は、「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」と規定しています。条文上は母も認知権を有しているのですが、母の場合は出産行為があるので、嫡出でない子についての母の認知は不要と考えられています。従って、問題となるのは父による認知ということになります。
任意に認知をするには、戸籍法に定めている届け出をする必要があります。この届け出行為をしないと任意認知にはなりません。また、民法の規定では、遺言でも認知することができるとされています。テレビドラマで、遺言書を開封してみたら、ある人を自分の子だと認知して、相続人たちが驚くシーンがありますが、法的にもあり得るシーンということです。
ただ、遺言による認知の場合、誰が認知届を提出するのかですが、それを担当するのは遺言執行者ということになっていますので、遺言による認知のときには遺言執行者を指定しておいた方がいいでしょう。
認知をする側の能力ですが、未成年者または成年被後見人であっても、法定代理人の同意なしに認知ができるとされています。ただ、認知の意味が分からない状況で認知をしても、その認知の有効性が争われますし、判断力がまったくない状況であれば、その認知は無効と考えられています。
次回も認知の説明をします。